音楽ライターの二木信が、この困難な時代(Hard Times)をたくましく、しなやかに生きる人物や友人たち(Good Friends)を紹介していく連載「good friends, hard times」。国内のヒップホップに軸足を置きながら執筆活動を展開してきた二木が、主にその世界やその周辺の音楽文化、はたまたそれ以外の世界で活躍、躍動、奔走するプレイヤー(ラッパー/ビートメイカー/DJ)、A&Rやプロデューサーなど様々な人物を通じて音楽のいまと、いまの時代をサヴァイヴするヒントを探ります。
第7回目にご紹介するのは東京・高円寺にあるヴェニュー「SUB store」。(Qetic編集部)
東京・高円寺にある「SUB store」という一風変わったヴェニューを紹介したい。場所は高円寺北口の中通り商店街の餃子の王将を左に曲がり路地を数十メートルほど歩いて左手のビルの2階。インドネシア料理屋、コーヒーやお酒も楽しめて、週末を中心にライヴやDJを中心としたパーティも行われている。店内を見渡すと、私物の音楽本やミュージシャンの自伝、ジェイムズ・ブラウンのフィギュア、マルコム・Xの演説を用いたエレクトロの名曲“NO SELL OUT”のステッカー、ガールズのサイン入りのファースト『アルバム』やビヨーク『ユートピア』のレコード・ジャケットも飾られている。DJやお店の常連客のレコードの委託販売も行っていて、アフリカ音楽を始めとするワールド・ミュージックやパンク、シティ・ポップなどジャンルも幅広い。

お店を切り盛りするのはインドネシア出身のアンディと久実さん夫妻。そもそも「SUB store」はどのようにできたのだろうか。ロックやパンク、ハードコアやスケートが大好きだったアンディは東京各地のライヴ・ハウスやレコード屋を渡り歩くなかで、音楽やサブカルチャーが根付く高円寺の魅力に引かれて、2014年に当地への引っ越しを決意する。高円寺にまったく縁のなかった久実さんは「アンディにこの町の面白さを教えてもらいましたね」と語る。そして引っ越し後にお店をやろうと思い立ち、ふたりで仕事を辞め、2016年3月に「SUB store」をオープン。


中野、阿佐ヶ谷、下北沢でも物件を探したというが、最終的に高円寺に決めた理由は何だったのか。「高円寺の小さい駅のサイズも良かったし、雨でも駅から濡れないで歩いて来られる高架下に近い物件が見つかったのもありますね。あと家賃が安かった。最初は隣がヤクザの事務所でしたけど、まあ大丈夫でしたよ(笑)」とアンディ。
店名は、アメリカのシアトルのインディ・レーベル〈SUB POP〉に由来。レーベルの大ファンだったアンディと彼の弟が名前を決めた。お店のロゴもオマージュだ。「だけど、ロゴのフォントもデザインも違うからコピーじゃなくてインスパイアですね」と元々グラフィック・デザイナーが本職の彼は言う。〈SUB POP〉のTwitterアカウントに「大ファンなのでインスパイアされた」という旨のDMを送ったところアンサーが返ってきたという。「ぜんぜん怒られることもなくて。むしろTwitterでフォロー・バックしてくれてちょっと応援してくれている感じですね」と久実さん。
small、unique、bookという頭文字から成る「SUB」にはお店のコンセプトが込められている。「お店は小さくて、ユニークでありたくて、しかも本が大好きだからです」とアンディが簡潔に説明してくる。HPには次のように記してある。「幅広い年齢の方々がサブストアで新しいアイデアや文化に出会ったり、お互いに情報交換することで世界のアートや音楽、文化の新しい面に触れていただければ嬉しいと思います」。

じつは高円寺の店舗は4号店。2014年にアンディが出資、彼がレコードやCD、音楽グッズのバイヤーの役割を担い、弟夫婦がジャカルタに1号店を設立した。翌2015年初頭にバンドゥンに2号店、同年の後半にバリに3号店を開き、さらに2019年にはジョグジャカルタに5号店をオープンした。もちろん現地にはそれぞれビジネス・パートナーがいる。現在は、バリ、高円寺、ジョグジャカルタが開業中で、バンドゥンのお店も再開する予定だ。
当初、高円寺の「SUB store」では絵や作品の展示会などは念頭にあったものの、ライヴやDJのパーティまでは想定しておらず、いまあるDJ機材や大きなスピーカーもなかった。久実さんは最初、コーヒーがメインのお店と考えていたそうで、料理のメニューも最初は3種類程度だった。本格的に料理を提供したり、お酒を作ったりする飲食業そのものが初めてのふたりは手探りでお店の営業を模索してきた。

「お客さんからインドネシア料理をもっと増やしたほうがいいよとアドバイスをもらってちょっとずつ頑張って増やして行ったり。DJイヴェントをやるようになったのもお客さんが勧めてくれたからですね。お店が盛り上がるよって」(久実)。
「最初にDJイヴェントをやってくれたのは大槻洋治さんという方です。アフリカン・ミュージックのレコードのコレクターで、ワールド・ミュージックのパーティをやってくれました」(アンディ)。




大槻さんは西アフリカのマリで学んだアフリカン・スタイルのギターを弾くミュージシャンで、Youzy名義で主に60、70年代の西アフリカのレアなレコード等をプレイする。店内では大槻さん所有のレコードも売られている。
「だから、お客さんに助けられながら営業してきた感じです。そう、のでぃさんもオープン当初に来店してくれたひとりです」(久実)
のでぃとは、高円寺を拠点に活動する、知る人ぞ知るサイケデリック・ロック・バンド「ねたのよい」のヴォーカル/ギターで、サイケデリック・ロックを地で行く風貌とヒッピー・ファッションからいちど会ったら忘れられない高円寺アンダーグラウンドの重要人物だ。
ある日アンディがオープン時間の昼12時ぐらいに、イサーン音楽/モーラムをかけながら階段を掃除していると、ワインを瓶でラッパ飲みしながらタバコを喫って店の前に佇んでいるタトゥーの目立つ男がいた。それが、のでぃだった。
「私が恐る恐る『Nice to meet you…』と話しかけると、『良い音楽かけてるね。俺もタイの音楽が大好きだから明日レコードを持って店に来るよ』と言われて。でも、タンクトップですごいタトゥーも見えているし最初は怖いじゃないですか。隣はヤクザの事務所だし、タトゥーの人は来るし、『高円寺はプロブレムだらけだ!』って思いましたね(笑)」とアンディが冗談めかして言う。
翌日、実際にのでぃが大量に持って来たタイの音楽の7インチはすべてオリジナル盤の貴重なレコードだったという。そうして意気投合したふたりはRADIO SAWADEE(ラジオ・サワディ)というDJユニットを組むに至る。そして、2021年に立ち上げた「SUB store」の音楽レーベル部門〈SUB Records〉の第一弾としてリリースしたのが、ねたのよいのファースト・アルバム『月桃荘』(06年)のLP盤だった。
ねたのよい(NETANOYOI)- 月桃荘
こうした「SUB store」の交流のネットワークは高円寺ローカル、東京、日本、インドネシアだけに限定されない。
「フェスや大きなライヴで来日した海外アーティストから、うちのお店ぐらいの狭い場所でファンと近い距離でインティメイト・ライヴ(親密なライヴ)をやりたいという連絡がいっぱい来るようになって。英語が通じるのも大きかったでしょうし、サブカルチャーが根付いた高円寺というネーム・ヴァリューが世界に広がっているのを感じました」(久実)。
これまでに、アメリカのロック・バンド、!!!(Chk Chk Chk)の元メンバーのアラン・ウィルソンがYolo Biafra名義でDJしたほか、UKのジャズ・ファンクのグループ、インコグニートのリード・ギタリスト、フランシスコ・サレス、あるいはフィンランドのシンセ・ポップを奏でるヤーコ・エイノ・カレヴィというアーティストなどがライヴを行っている。ちなみに、ビョークが2022年に発表したアルバム『フォソーラ』への参加で注目を集め、今年9月の来日ツアーも話題となったインドネシアのエレクトロニック・ミュージックのユニット、ガバ・モーダス・オペランディは、アンディの友人でもある。「彼らが急に有名になってびっくりした。すごいね」と笑う。
Gabber Modus Operandi(LIVE)|HÖR – Jun 20/2023
「SUB store」のお店の雰囲気は開放的で、久実さんとアンディはとてもフレンドリーで、音楽やアートのジャンルも幅広く、そのネットワークも豊かだ。しかしとうぜん、「何でもあり」というスタンスで営業しているわけではない。そこには理念がある。
「大事にしているのは金儲けだけのためのビジネスはやらないことです。資本主義はやっぱり嫌いだから」と久実さんがきっぱりと言う。「例えば、うちで展示をやる場合は1週間5千円か8千円という安めの値段に設定していますけど、良い作品であることは前提です。たとえば、台湾や中国の友達もいるし、中国と台湾の国同士の対立の問題で友だちが困っていればできる限りのサポートはしたい。自分たちだけ良ければ良いというビジネスはしたくないですね。社会にもちゃんと貢献できるソーシャル・エンタープライズをやっていきたい」。

アンディが付け加える。「レコードもできるだけ安く売りたい。高くても2千円台、できれば千円か七百円ぐらいで売るのが理想。それでは利益がなかなか生まれないけれど、その方がお客さんも私もレコードもハッピーですよね。物を高く売るより、お店を通してコミュニティを作ることの方が大事です」
ライターやタレントとしても活躍するマシュー・チョジックが高円寺のカルチャーとこの土地のフッド感覚とノスタルジックな魅力を紹介する動画で水先案内人になっているのがアンディだ。また、『バンドやめようぜ! ──あるイギリス人のディープな現代日本ポップ・ロック界探検記』(ele-king books)の著者、イアン・F・マーティンも〈SUB store〉をたまに訪れるという。そのイアンは2019年9月におこなわれた高円寺の再開発反対のサウンド・デモのレポート(https://www.ele-king.net/columns/007332/)を書き残している。そして、店内には2022年5月の同様のアクションを報じた『THE JAPAN TIMES』の切り抜きが貼られている。

NHK World – Koenji:A Nostalgic Neighborhood.
高円寺北口にある庚申通りには、「SUB store」と縁の深い、ポスト・パンクやポスト・ロック、実験音楽や電子音楽、中国のアンダーグラウンドの作品などを置くレコード店〈UPTOWN RECORDS〉がある。2011年にサンフランシスコ出身のサッコ(SACCO)と上海出身のソフィア(Sophia)が上海にオープン、2020年に高円寺に新店舗ができた。当初はふたりで来日して開店する予定だったが、中国がコロナでロックダウン(都市封鎖)したためにソフィアが出国できず、サッコは見知らぬ土地にひとりで来日してお店を始めた。〈UPTOWN RECORDS〉はレコードを売るだけでなく、「SUB store」同様にお酒を提供したりDJのパーティも開いたりするため、コロナでとうぜん営業も打撃を受けた。そこで、不慣れな環境で苦労していたサッコをさまざまな面からフォローしたのが「SUB store」のふたりだった。
「コロナで外に出られないことで私は高円寺の人たちとより仲良くなれた気がしますね。お互い助け合わないといけなかったし、それで仲が深まった感じがします。高円寺はちょっと村っぽいというか、助け合いで成り立っている町だと思う。もちろんいろんな人たちがいますけど、自分たちの周りはそうですね。やりたいことをやっていれば、必ずそれを好きな人とつながっていくし、そこから何かが広がっていく。自分にとってはそういう町です」(久実)
「SUB store」という一風変わったヴェニューは、音楽/文化的に一見マニアックなように見えて、じつは敷居が低く、入りやすい。それは、何をおいても、できるかぎりフォローし合いながら生きていくというごく真っ当な生活者意識がナチュラルに漂っているからだろう。いちど足を踏み入れたら予測不能な展開必至だ。
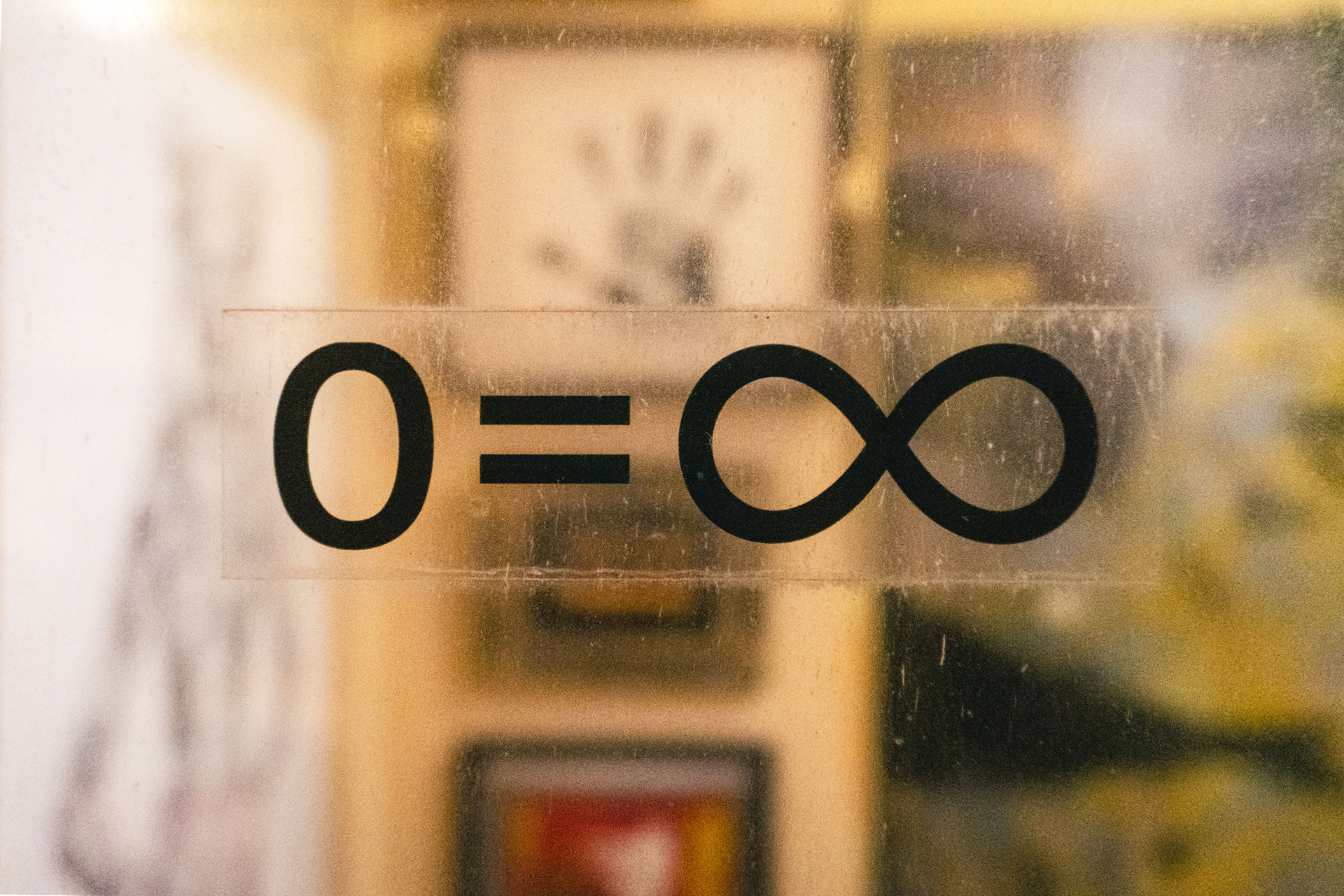


取材・文/二木信
編集・撮影/船津晃一朗
INFORMATION
SUB store
〒 166-0002 東京都杉並区高円寺北3-1-12宮應北ビル2階
OPENING HOURS
WED – SUN from 5PM – 11PM
Monday & Tuesday is Holiday