4人組ロックバンド、DATSのニュー・アルバム『School』がリリースされる。前作『Digital Analog Translation System』からおよそ2年ぶりとなる本作は、新型コロナウイルスの感染が世界中で広がる中、完全リモートにてレコーディングされたもの。
PERIMETRONのOSRINが手がけるMVも話題となった“Showtime”や、TAWINGSのCony Planktonがボーカルで参加した“Your Home”、キング・ハーベスト(King Harvest)がヒットさせたシャーマン・ケリー(Sherman Kelly)作曲の”Dancing in the moonlight”などを収録。あくまでも4人のバンド・アンサンブルを基軸としつつ、ロックやエレクトロ、ヒップホップなどクロスオーバーしていくこれまでのサウンド・プロダクションをさらに追求した内容に仕上がっている。
先日、SONYPARKにて無料配信ライブを行ったDATS。およそ9ヶ月ぶりにメンバーと音を合わせ、「バンドの大切さを身に染みて感じた」とインタビューで語ってくれたボーカルのMONJOEに、本作『School』の制作秘話やタイトルに込めた想い、コロナ禍で思ったことなどじっくりと聞いた。
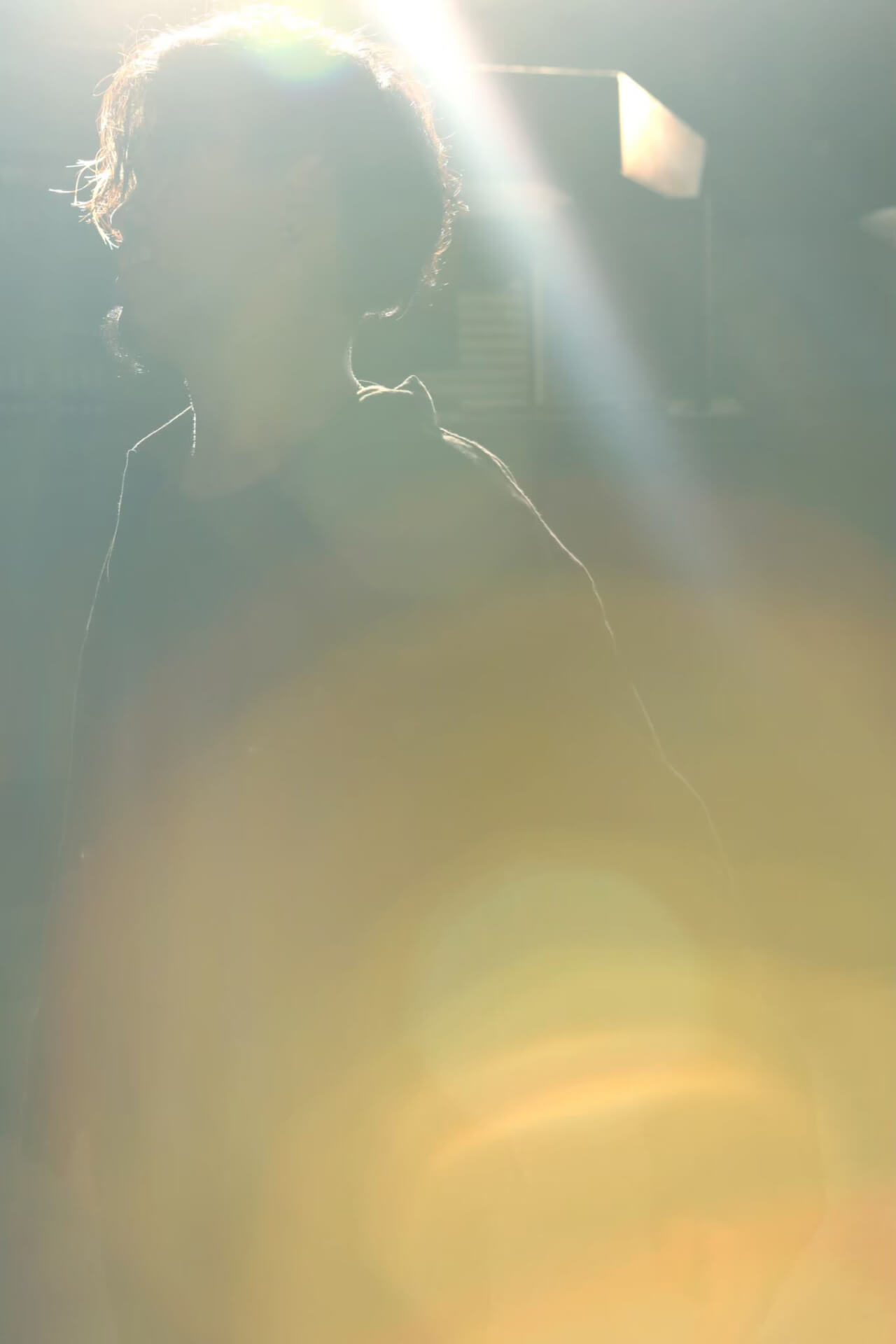
Interview:
MONJOE(DATS)
──先日、SONYPARKで開催された配信ライブはいかがでしたか?
演奏自体9ヶ月ぶりだったので、シンプルに楽しかったです。「やっぱり、バンドっていいな」と素直に思いましたね。
ただ、お客さんがいないのはやっぱり寂しかったし、実際のライブと配信ライブは同列で語ることはできないなと思いました。ライブの配信というよりは、生のレコーディングを配信しているような感覚で。それをどこまでコンテンツとしてクオリティを上げることができるのかも考えさせられました。
──確かにコロナ禍になってからの半年で、配信ライブのあり方は日々更新されていますよね。おそらく今後も「配信ならではのコンテンツ」として突き詰められていくと思いますが、それは決して「ライブの代替物」にはならないことも痛感させられたというか。
その通りだと思います。生演奏の場合は空気の振動を体で感じることができますが、配信の場合はライン出力の音声をモバイル機器のスピーカーで聴く人もいるわけですし、それはライブの臨場感には敵うわけがないな、と。そうすると「ライブじゃなくていいじゃん」という話になっていきそうですよね。そこに対しての向き合い方、価値の見出し方については、今後もっと考えていかなければと思いました。
──ライブの翌日、Twitterに「自分としては『感染拡大に加担したくない』というスタンスは9月になった今でも変わらない」と呟いていましたよね。3月のTweetを引用する形での呟きでしたが、どんな思いだったのでしょうか。
ライブを終えて、改めて思った気持ちですね。ライブ中はお客さんがいなくて寂しい気持ちもあったのですが、それでもまだ慎重に行動したいという気持ちです。
自分としては「感染拡大に加担したくない」というスタンスは9月になった今でも変わらない。気にしすぎだと笑われたりもするけど、見て見ぬフリをして過ごすことができない。
お前にとって大切なものってそんぐらいのもんなの?って自問する日々。だからこそ、もどかしい。 https://t.co/5yLOWAR64E— MONJOE (@monjoe_) September 5, 2020
──実際のところ、コロナ禍でどのような日々を送っていましたか?
予定されていたライブがなくなり、友人と会うのも極力避けて、外出も必要最小限に留めていました。海外で実施されていたロックダウンの基準を、自分に強いて行動していましたね(笑)。しかも、割と早い段階から警戒していたんですよ。2月に入ってすぐ武漢での感染がニュースになった頃から「これはやばいな」と。ただ、周りはみんな「まあ、大丈夫でしょ」みたいな感じで、むしろ僕の方が笑われるレベルでしたが。
──コロナへの向き合い方は、立場や考え方によっても温度差がありましたよね。
本当にその通りで、誰がどのような考え方をしているからといって、それを責められるわけもないし責めるつもりもなかったです。人それぞれ、自分の信念に基づいて生活していくしかないですよね、これからも。海外の状況を見ていると余計にそう思います。
海外に住む友人からの情報だと、日本と比べるとめちゃくちゃ厳しくて、外出したら逮捕されちゃうような国もある。「日本は(ロックダウンになっていないから)大丈夫なんだと思っていたよ」と言われるんです。別に日本も、「大丈夫」ではなかったと思うんですけど(笑)。海外に比べて規制が緩いし、自由ではありましたが。
──〈#SaveOurSpace〉の発起人の一人は篠田ミルさん(yahyel)でした。彼らの運動についてはどのような見解でしたか?
もちろん賛同しましたし、署名もしました。ただ〈#SaveOurSpace〉にしても、SNS上でのハッシュタグ運動にしても、流行りに乗っかる形で全然いいんですけど、せっかくその問題に関心を持ったのならその場限りで終わるのではなくて、その後の経緯などもちゃんと見届けた方がいいのではとは思っていました。そこは発信側としても「課題」の一つではあると思います。
──「課題」というのは?
例えば、運動の中で特定の政治家を誹謗中傷したり、強い言葉で批判したりする人がいると、運動全体がそういうイメージになってしまうじゃないですか。あるいはデモ活動にしても、暴力的な側面ばかりが映し出されてしまって、そこで表明している主張やメッセージまで歪んで伝えられてしまうこともあったりして。そういう状況を見ていて悲しい気持ちになりましたね。
──わかります。身内同士のガス抜きが目的ではなく不特定多数の人にメッセージを届けたいのであれば、ましてや自分と違う立場の人を振り向かせたいのであれば、その伝え方や見せ方はとても大切です。にも関わらず、言動がどんどん先鋭化していき、結果的に無党派層が離れていく場面を今回たくさん目にしました。
一人ひとりはとても優しかったり、そこで訴えている主張やメッセージが頷けるものだとしても、おっしゃるように伝え方や見せ方を考えないと、世の中を大きく変えていく事は難しいんじゃないかと思います。「小さな村」みたいになってしまい、身内に甘いというか、自浄作用が働かなくなってしまっている様子を残念に思うこともありましたね。
コロナ禍になってより強く思ったことは、その意見を支持するしないにかかわらず、「自分はこう思っています」というステイトメントを明確に示す人たちに、自分はより強く惹かれるのだなということ。そういう人たちが作る音楽は、純粋に「聴いてみたい」と思う。どんなことを考えているのか、どういうライフスタイルなのか、どのような葛藤を経て今の思想にたどり着いたのか、アーティストのパーソナルな部分により興味が湧いてきているのかもしれないです。
──そういう意味で、最近気になったアーティストというと?
The 1975。音楽の素晴らしさはもちろんのこと、マシュー・ヒーリー(Matthew Healy、Vo)のパーソナルな部分が、曲を通して垣間見えるし、だからこそ追ってみたくなる。彼らが所属している〈Dirty Hit〉のアーティストたちって、そういう傾向にある人が多い印象ですね。志を同じくする人たちが自然と集まってきているのかもしれない。音楽家として、ライフスタイルも政治的なステイトメントも同じ距離感でナチュラルに発しているところに憧れますね。自分たちもそういうスタンスでありたいと思います。
──「ブラック・ライヴズ・マター運動(以下、BLM)」については、どう思いましたか?
例えば大坂なおみさんに関する一連の出来事を見ていると、BLMの概念が日本ではちゃんと伝わっていないし、そもそも馴染みのないことなんだろうなと思います。しかも、色々な考えの人がいすぎて収拾がつかなくなっている。僕は出身がアメリカで、小学生時代の3年間をアメリカで暮らしていたのもあり、人種差別に対するセンシティブさを身にしみて体感しているので、大坂選手に絡んでいる人たちの行為にはびっくりします。しかも、全く悪意がないわけですよね。
──悪意どころか、本人は善意のつもりで絡んでいる可能性が大きいですよね。
ただ、BLMのキャンペーン化に関してはアメリカ国内でも賛否が別れていますし、黒人の中にも批判的な意見はある。その場所に住んでいて、その場所で生活している人にしか分からない感覚もあるから、外野である僕らがどうこう言える話ではないのかもしれません。ただ、シンプルに人種差別はダメです。
──そういったコロナ禍で起きた出来事が、MONJOEさんの活動や作品そのものに何か影響を与えていますか?
作品を作る上での後押しにはなっていますが、直接な影響でというと歌詞です。サウンド自体はコロナ以前から抱えていた課題や、「こういうことをやってみたいよね」みたいなビジョンがあったので、それを突き詰めていく中で出来上がったものでした。
──コロナ以前から抱えていた課題とは、どういうものですか?
「そもそも自分たちって、何なんだろう?」という基本的な部分ですね。「DATSといえば、これだよね」みたいな「DATS節」を模索していました。これまでは、良くも悪くもそこがはっきりしていなかったからこそ、色んなことにチャレンジできていた部分があると思います。その上で、やはり「核」となるものが欲しくて。それで出た答えが、アルバムタイトルにもなっている『School』ということでした。ある種の「スクール感」みたいなものが、DATSの核なのではないかと。
DATS – Showtime
──「スクール感」ですか。
「スクール」で連想するものだと、例えば「学校」「青春」「キラキラした」「懐かしい」「エモい」みたいな要素だと思うんです。「スクール」という言葉によって、DATSが求めていた全てをパッケージできていたんです。それに気づいた時からメンバー内での標語としても使われていました。例えば何かの曲を聴いて、「これってスクールっぽいよね」みたいなことを言い合ったりして(笑)。
毎週、みんなで会うときにオススメの曲など紹介しあっているんですけど、そこでも「この曲ってスクールだよね」「このバンドはスクール感ゼロだな」みたいな仕分けが全員できるところまで、基準として残るものになりました(笑)。どうせだったら、その基準をもとに今回自分たちのアルバムを作ってみようと。
──アルバム制作はいつ頃から始まったのですか?
曲の骨組みは去年の時点で揃っていましたが、レコーディングは全て今年に入ってからです。ただ、こういう状況だったので直接会うことはできず、リモートで行いました。骨組みとなるデモ音源があって、それをメンバーに投げてドラムを入れてもらったり、ベースを入れてもらったりしながら詰めていくやり方です。必要な時は、Zoomなどで話し合いました。
──特に不便などは感じませんでしたか?
それどころか、むしろ今までより効率的だったかなと思いますね。
──例えば“Showtime”の歌詞は、コロナ禍やSNS騒動の影響によって書かれたものだと思いました。
この曲、実は個人的な「喧嘩」について歌っているんです。ある人と、実に他愛もない理由で喧嘩が始まって、次第にヒートアップし大事になってしまったことを歌詞にしています。意地になって言い返したりしている様子が、俯瞰すると何かのショーを観ているようだなと思ったことがモチーフになっているんですよね。
なので、コロナ禍やSNS騒動のことは意識していなかったんですけど、もしかしたら無意識のうちに影響されているところもあるのかもしれない。実際、Twitterを見ていると、言わなくてもいいようなトゲのある言葉が飛び交ったり、負の感情の吐きダメになっていたりするような状況で。おっしゃるように、確かにリンクしているようなフレーズがありますよね。
──そう思います。例えば、《くだらないプライドを綺麗に並べるショーウィンドウ》や、《言葉にしないでいい言葉の威力にさえ 気付けず傷つけたりもして》といったラインはSNS騒動のことにも読めるし、《後悔の無いようにって言うのに こんなことになるなんてさ》も、コロナ禍の状況を歌っているようにも聞こえます。
確かにそうですね。自分でもびっくりしています(笑)。
──ちなみにこの曲は、PERIMETRONのOSRINさんが手がけたMVも話題になっていますね。OSRINさんは、この映像についてTwitterで、「自分勝手な生き物との話。周りからすったもんだ言われようと 踊ってる時は繋がってる。それでいいね」とコメントしていました。今津良樹さんのアニメーションもとても印象的です。
OSRINとは一度だけ打ち合わせしたのですが、今話したような楽曲の成り立ちについて話しただけで、あとはお任せしました。歌詞の内容をそのままなぞるのではなく、彼なりに解釈したことを映像化してくれたのが面白かったです。一つの楽曲に対していろんな解釈ができるということは、自分としては良いものが出来たのだなと思えましたし。
Showtime / DATS
Music Video 監督しました。https://t.co/cEQqgVCKAB自分勝手な生き物との話。
周りからすったもんだ言われようと踊ってる時は繋がってる。
それでいいね。アニメを描いてくれた@ImazuYoshiki さんの鬼粘り、
コンプしていてとっても暖かかったです。あー楽しかった。 pic.twitter.com/UZ1toIajPa
— takemichi“osrin”kawachi (@osrin_kawachi) August 12, 2020
DATS – Showtime
──確かに。OSRINさん視点が加わったことで、この曲の深みがさらに増したように思います。TAWINGSのCony Planktonさんをフィーチャーした“Your Home”は、どのように作っていったのですか?
曲ができた時に、女性の声が合うメロディだなと思いました。それで誰にお願いしようか考えていた時、たまたまTAWINGSの”水仙”を車の中で聴いて、すごく良くてオファーしたところ快諾してもらいました。
それこそ歌詞は、緊急事態宣言が解除された直後くらいに書いたもの。コロナ禍になって無駄なものがどんどん省かれていき、自分たちの人生を豊かにしていたものが、いつの間にか切り捨てられている状況の中、DATSというバンドが「最後の砦」というか、いつでも帰って来られる「家」のような存在であって欲しいという願いを込めています。
──“Your Home”のHomeは、文字通りの家でもあるし、バンドでもあり、それぞれの人の内面でもあると。
はい。Conyの声にもある種の包容力を感じるし、アルバムの中でいいアクセントにもなっている。自分にとって、お気に入りの曲になりましたね。
──“Dancing in the moonlight”は、キング・ハーベストがヒットさせたシャーマン・ケリー作のカヴァーです。これを取り上げたのは?
キング・ハーベストではなくトップローダー(Toploader)のアレンジをもとにカヴァーしたのですが、初めて聞いた時から「いいカヴァーができそうだな」と思ったんですよ。歌い方やアレンジにロックな要素が大きく、そのスタイルが自分にも通じるものがあるなと。DATSや僕自身にとって、「ロック」は切っても切り離せない要素だなとカヴァーして改めて思いました。
Toploader – Dancing in the Moonlight
──「ロック」といえば、冒頭曲“Time Machine”は歌詞の中にオアシス(Oasis)の曲名やニルヴァーナ(Nirvana)の名前を入れるなど、90年代ロックへの憧憬がストレートに表れていますよね。
僕にとって90年代は、物心がつく前の時代なんです。「青春時代を90年代に過ごせたら良かったのに」なんて時々思うくらい憧れてはいます(笑)。スマホやネットがないあの時代に、もしコロナ禍になって街が封鎖されたらどうなっていただろう? とも思うんですよね。そんなことを想像しながら書いた曲です。
──なるほど。「憧憬」だけでない絶妙な距離感が表れていますね。
さっき「無駄」について話しましたが、90年代は「無駄」なものが今よりもたくさんあったのかなと。そこは純粋に憧れます。バンドとか「無駄」の塊だと思うし(笑)。そういうものを愛しているからこそ、ヒップホップやDTMミュージック、プロデューサー・アーティストなどが台頭しているこのストリーミング時代に「バンド」による音楽を、どういうポジションで、どうやって届けていけばいいのかをすごく考えます。そういう意味でも「バンドの意地」のようなものを、一つのステイトメントとして今後もDATSで示していけたらいいなと思っていますね。
──ちなみにオアシスは「スクール」ですか?
えー! どうだろう……うちのギターの吉田巧がめちゃくちゃオアシス・マニアなので、ちょっと安易な回答はできないな(笑)。彼に怒られるかもしれないけど、僕はオアシスを「スクール」だと思っていますね。
──ありがとうございます(笑)。では最後に、本作を作り終えた心境を改めてお聞かせください。
今までのDATSはSNS社会のリアルな日常とか、デジタルとアナログの共存性とか、そういうソーシャルイシューを描写するようなコンセプチャルな作り方をしていたんですけど、今作は、あくまでも自分の日常における経験や、些細な出来事から感じた思いを自分の言葉で歌詞にしています。たとえるなら、日記に音楽をつけたような作品になりました。
結果的に、それがこのソーシャルな時代を生きる人を代弁する作品になっていれば、それはそれで嬉しいし、そういうふうに思えなかったとしても、この時代に生まれた一つの「リアルな声」であることには間違いない。バンドとしても、新しい境地に踏み出すことが出来た作品だと思っています。
Text by Takanori Kuroda

DATS
トラックメイクを手掛ける MONJOE(Vo./Syn.)を中心に 2013 年結成されたロックバンド。結成翌年には「出れんの!?サマソニ」にてク リマン賞を受賞。2015 年には 2 度目のサマーソニックに出演を果たし、デビューEP「DIVE」をリリース。2017 年には、砂原良徳氏を マスタリング・エンジニに迎えたテビュ゙ー・アルバム『Application』を発表。その直後に開催された FUJI ROCK FESTIVAL をはじめ、 次々と国内の大型フェスに出演し、その圧倒的なパフォーマンスが各方面より高く評価される。2018 年 6 月、SME レコーズより、 本編の全曲リミックスを付属したダブルアルバム『Digital Analog Translation System』でメジャーデビュー。2019 年 5 月にメジャー第 2 弾となる EP『オドラサレテル』をリリース、続く 11 月には初のアニメタイアップ楽曲となる「Game Over」(TV アニメ「ノーガンズ・ラ イフ」)EDテーマ)をメジャー初のシングルとしてリリース。
