——ここからは、20周年ということで、これまでの20年を振り返って、主に音楽性の面にフォーカスしてお聞きしたいと思います。まず97年のデビューEP『覚醒』の時点で、バンドが志していた音楽はどういったものでしたか?
田中 たぶん、音楽の趣味自体は同世代よりは渋い方だったと思うんですよね。クラシック・ロックというか、ルーツ・ロックというか、そういった匂いがしたほうがよいという意識は絶対的にあった。それとは裏腹に、メロディはポップにしたいとも思っていた。その感じが『覚醒』には詰まってるんじゃないでしょうかね。
——今聴くと、ブリット・ポップ以降のブリティッシュ・ロックのニュアンスも強く感じるんですが、同時代の海外の音楽はどれくらい聴いていましたか?
田中 そこそこ聴いてたんですけど、「すごいオアシスっぽいね」と言われることも多かったんで、「オアシス嫌いです」とか言ったりしてました(笑)。
西川 僕オアシスは最初のアルバムしか聴いてなかったんですよ。そこから最近のアルバムまで聴いたことなかったです。でも、ブラーとかは聴いてました。
田中 どっちかっていうとブラーの方が好きやったよな。
西川 当時は、もっとローファイなサウンドを一生懸命作ろうとしてましたね。
田中 当時で言えばオーシャン・カラー・シーンとかの「ポール・ウェラー・ファミリー」みたいな、もっと渋い見られ方を望んでたんじゃないかな。

——それからデビュー・アルバム『退屈の花』を98年、2nd『Lifetime』を99年にリリースします。この頃は商業的にも上り調子で、音楽面でも『覚醒』から続くバンドの核を少しずつ拡張していったような印象があります。
西川 こう、ほぐしていく作業っていうのは、当時のディレクターの方が熱心にやってくれたことで、そのために根岸孝旨さんというプロデューサーを呼んできたっていうのは大きかったと思います。根岸さんと一緒にやったのはターニングポイントになりましたね。
GRAPEVINE – 君を待つ間
GRAPEVINE – スロウ
——ほぐしていく作業とは、具体的にどういったことですか?
西川 僕らは、ある意味すごく意固地なところがあって、見せ方にしろ、聴かせ方にしろこういう音楽はあんまり好きじゃないとかが多かった。そういうものだけじゃないってことを教えてもらった感じですね。たぶん、当時のディレクターはそれに一生懸命だったんじゃないですか。このままでは幅が狭くなってしまうって危惧していたんだと思います。
——当時、好きじゃなかったものっていうのは?
西川 どっちかっていうと、日本のものはあんまり。すごく日本的だなって思うものを嫌ってたと思います。歌謡曲に聴こえるんじゃないかっていう。
田中 まぁ、今でもそのきらいはあるけどな。
亀井 あの当時、バンド自体が多かったから差別化を図りたいみたいなのもありましたね。
——90年代後半は、バンド・ブームみたいな感じもありましたからね。
西川 でも、逆にオシャレに聴こえるのも嫌ってたような気がします。これ、ちょっとオシャレやなってことは、当時は絶対にやらなかったです。もっと男らしく聴かせたいというか。今は全然そんなことないんですけどね。むしろオシャレな方がいいなぁって(笑)。
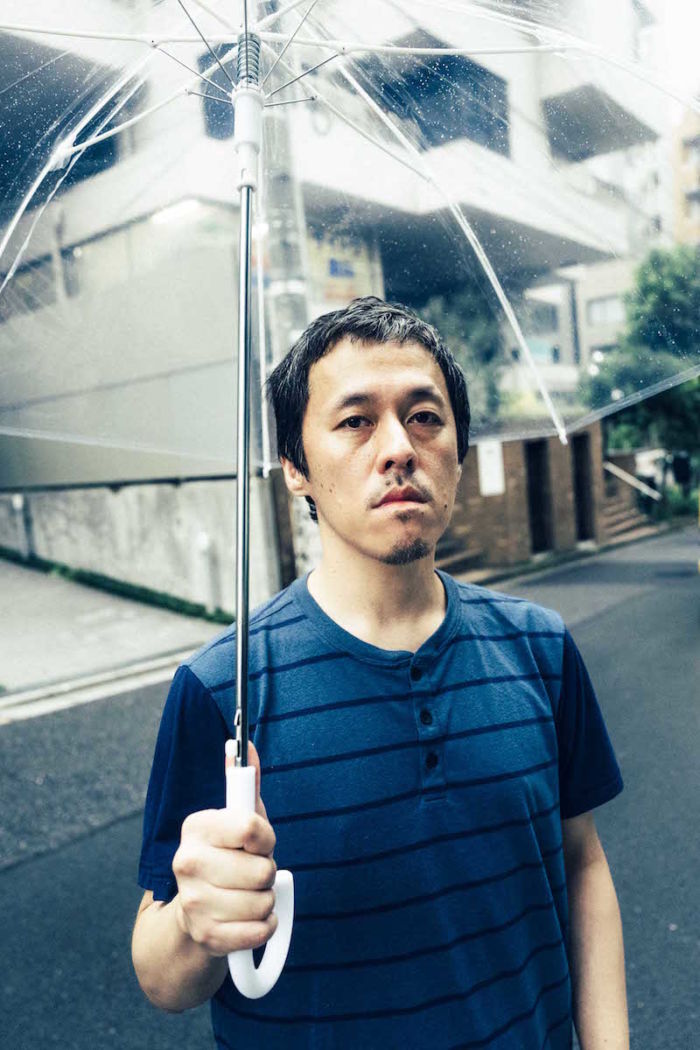
田中 今ではオシャレなことやってもオシャレに見えへんからな、俺ら(笑)。
——ははは! でも、そんな中で、バンドとしてはブレイク・ポイントを迎えるわけですよね。
田中 それは根岸さんの功績が結構大きかったと思いますね。同時にその頃、亀井くんのソングライティングが花開いていくわけで、結果として幅が広がったという。その前から、もちろん良い曲は作ってくれてたんですけど、根岸さんとの相乗効果でグッと可能性が広がったというか。
——続く3rd『Here』は、マスタリングに世界最高峰のエンジニアであるボブ・ラディッグが起用されていますが、彼に依頼したのはどういう経緯ですか?
田中 それも根岸さんなんです。ちなみに、マスタリングはボブ・ラディッグで、レコーディングとミックスに関しては数曲でトム・デュラックがやってくれていて。確か、その前に根岸さんがくるりと一緒にトム・デュラックからボブ・ラディッグという流れでやっていて、感触が良かったっていうことで、だったらそのコースでお願いしようかという話になったんだと思います。
——最終的に上がってきたものを聴かれて、どういう感想でしたか?
田中 やっぱり、トリートメントが洋楽的という感じでした。だから、音でいうと『Here』は抜けてますよね。『Lifetime』と比べても、全然違う感触でしたね。
GRAPEVINE – 羽根
——次の4th『Circulator』では、西原さんがバンドを休止して、3人での製作となり、サウンドも大きく変化したと思います。今聴くと、試行錯誤の時期だったんじゃないかという印象もありますが。
田中 そうですね。楽曲の幅もアレンジの幅もかなり広がってると思うんですけど、印象が閉塞的ですよね。
亀井 その時期、シングルのリリースが詰まってて、『Circulator』にはシングル曲がかなり入ってるんですよね。収録曲も多くて、よくそんなにいっぱい作ってたなと思いますね(笑)
田中 尺も長いんですよね。だから、聴くのしんどいんです。
——ギュッと詰まってる印象はありますね。ただ、ビートルズの中期から後期の作品とか、ビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』に通じるような密室的な実験性も感じられます。
田中 ちょうど西原誠が休むっていうので、どうせ三人でやらないといけないんであれば、いったん西原誠っぽいことは置いといて、根岸さんがベースを弾く前提でやれることをいろいろ試してみようっていう感じで作ってたのは間違いないです。
——ドラムを打ち込みで作ったり、あらきゆうこさんに入ってもらってツイン・ドラムの楽曲があったりと、リズム・セクションでも色々試している印象があります。
田中 普段からいろんな音楽を聴いている中で、その頃には時代的にエレクトロとかも出てきてるし、レディオヘッドも『キッドA』を出した頃だったので、そういった影響もあったんでしょうね。
亀井 そう考えると、確かにこのアルバムはいろんなことをやってるなと思いますね。“風待ち”とかも、ドラムをすごい変な録り方したりしましたし。
田中 “風待ち”ですごい覚えてるのが、ビートルズの『アンソロジー』が出た時に、新曲として“フリー・アズ・ア・バード”が出たんですよね。それをジェフ・リンがプロデュースしてて、その「ジェフ・リン方式」を真似しようって言って、みんなで盛り上がってましたね。
The Beatles – Free As A Bird
——その後、5th『another sky』から高野勲さんがキーボードとして参加し、次の『イデアの水槽』からは高野さんと金戸覚さん(Ba)が加わり、今に続く5人体制になっていくわけですが、この当時のバンドの雰囲気はどのようなものでしたか?
田中 実は、その前の『Circulator』のアルバム・ツアーから2人に入ってもらってるんです。5人の体制は、そこが原点ですね。
亀井 ツアー終わってから一回西原さんが戻ってきて、『another sky』を作るんですけど、やっぱりちょっと弾けないことも多くて。このアルバムも苦労しましたね。
田中 レコーディング作品に関して言うと、実は『Here』の時点から根岸さんが弾いてる曲が多いんです。それで『Circulator』は丸々根岸さんが弾いてくれてて、『another sky』も半分くらいは根岸さんが弾いてて。そういうイレギュラーな作り方に慣れてきていて、むしろ他のミュージシャンと一緒にやることを我々も楽しんでましたし、それはそれで前向きではありましたね。そういう中で出来ることをやろうっていう感じで。
——『イデアの水槽』が初めてのセルフ・プロデュース作品となったのはどういう経緯ですか?
亀井 一ツアーを一緒に回ったメンバーで心機一転、新しいバンドとしてアルバムを作りましょうという感じではあったと思いますね。曲もいろいろと面白いものが集まってたし。今も一緒にやってくれているレコーディング・エンジニアの宮島(哲博)さんがプロデューサー的なこともやってくれました。
西川 当時、デビューからずっと一緒にやっていたディレクターさんも異動でいなくなって、プロデューサーの根岸さんもいなくなって、リーダー兼ベースもいなくなって、みんないなくなったんですよね。本当に新しい体制になったんですよ。
田中 セルフ・プロデュースにしたのはそういう理由だと思うんですよね。5人バンドとして、プロデューサー、アレンジャーみたいな、アレンジメントに口を出す人がたくさん増えたということで。宮島さんもそうですし、新たに入ってくれた2人のサポートもそうですし。これはセルフという形にした方がいいんじゃないかと。空元気かもしれませんけど、逆にかなりポジティブだったと思いますよ。そういった意味では、『イデア』作ってる時はバンド勢いがあったような気がします。
——次の『déraciné』では、“スカイライン”のようなカントリー調の曲だったり、“KINGDOM COME”や“GRAVEYARD”のようなブルージーな曲だったりと、よりアメリカのルーツ・ミュージックに近づいていった感覚があります。それは意識的なものでしたか?
田中 常にアルバムごとに色んな曲があればいいなと皆考えてるので、どこまで意識できてるかは分からないですけど。今から思えば、ルーツっぽい色が出てくるっていうのは、最初の頃もう少しスカして考えてたものを開き直りはじめたというか。最初はブリティッシュ寄りの匂いを装ってたけど、もっと泥臭いものだとか、アメリカンないなたさとかダサさが出てもいいんじゃないかというような開き直りがその辺から出てきたんじゃないかと思います。
亀井 その時期から長田さんが関わるようになったのも大きいですね。
——ここから09年の10th『TWANGS』まで、長田さんのプロデュースが続きます。長田さんと根岸さんのアプローチはどういう風に違いましたか?
亀井 長田さんは結構直感的というか、野性味あふれる感じです(笑)。
田中 で、根岸さんはジェントルなんです。女性シンガーをよく手がけてたっていうのもあるし、逆にそうやから女子によく呼ばれてたのかもしれませんし。色んなことを知ってて、具体的に分かりやすく教えてくれて。一方で長田さんは、どちらかというと見て学べみたいなタイプなんですよ。
亀井 でも、長田さんと根岸さんはDr.StrangeLoveってバンドを一緒にやってきてるんで、根本的な考え方は一緒なんですよね。
——GRAPEVINEの皆さんから理想のバンド像としてウィルコの名前が頻繁に挙がるようになったのも、この頃からだったかと思います。ウィルコの凄さを意識するようになったのはいつ頃からですか?
田中 やっぱり『ヤンキー・ホテル・フォックストロット』からじゃないですかね。初期のウィルコも大好きで、アンクル・トゥペロとかオルタナ・カントリーのムーヴメントも好きだったんですけど、あそこで変わったじゃないですか。多分ジム・オルークが良かったんやと思うんですけど、あのぶち壊れ方というか、あれにはかなり刺激を受けました。バンドで出来ることを模索してる感じというか、あの感じにはすごくシンパシーを抱きましたね。
Wilco – Jesus, etc
——バンドの10周年となった07年リリースの8th『From a small town』では、初めてジャム・セッションを通じて曲を作ることになりました。それまで、ジャム・セッションでの作曲を避けてきたのは何か理由があったんですか?
田中 いまいち具体的にやり方がどんなもんか、分かってなかったんですよ。たまたま全員が曲を書くバンドだったんで、それまでは誰かが持ってくる曲で成立しちゃってたんです。ただ、誰が持ってきた曲であっても最初の形から全く違うものへと変わっていくんで、結局ジャム・セッションで作ってるようなもんなんですけど。だから、そういう素質自体は持ってたんだと思うんです。長田さんの提案で「じゃあジャム・セッションでもやってみなよ」って話になったのがきっかけですね。
——ここからジャム・セッションで作る曲が増えていきますが、それは最初にやった時に手応えを感じられたということですか?
田中 そうですね。ビギナーズラックなのか何なのか、最初にできたのが“Fly”という曲なんですけど、高揚感もあって、これは家で作ろうと思ってもできないなって皆感じたんだと思います。
——ジャム・セッションでの楽曲が増えてきた影響もあると思いますが、この頃からより構築的なアプローチの楽曲が増えていった印象があります。この頃、参考にしていたり、よく聴いていた音楽はどういったものでしたか?
田中 ウィルコはよく聴いていた。あとブルックリン界隈とかもその辺りかな? ダーティ・プロジェクターズとか、グリズリー・ベアとか、あの辺のバンドは好きでよく聴いてましたね。
Dirty Projectors – Keep Your Name (Official Video)
Grizzly Bear – Two Weeks (music video in HD)
——2009年にはSXSWに参加して、ニューヨークでもライブを行いましたね。このアメリカでの経験はバンドにとってどのような刺激になりましたか?
田中 すごく刺激にはなりましたね。本当に美しい思い出です。もうあと10年若かったら海外進出もあり得たかなって思うくらい、刺激的でした。
——具体的に、日本でのライブとどういう違いを感じました?
亀井 お客さんがライブの楽しみ方をよく知ってるというか、すごい楽しもうとしてくれて、やってる方も盛り上がるんですよね。
田中 日本でやってることの居心地の悪さが一切なかったんですよね。俺ら全然これでええんやっていう。それこそ今回の<フジロック>もそうなんですけど、オーディエンスの反応とパフォーマンスってすごいダイレクトにリンクしてるんですよ。それはいわゆる予定調和なものとは全然違うんです。
西川 日本って、聴きに来る文化なんだと思うんですよ。それで、最後に終わったら拍手するという。紅白歌合戦を見てるのと同じ感覚というか。それに対して、向こうの人は第一に飲みに来てて、その場所でバンドがBGMを演奏してるという感じで。
田中 日本は、一挙手一投足を見逃さないように、固唾を飲んで見守る感じ。すごい盛り上がってるバンドであっても、その盛り上がり自体がパッケージ化されてるんですよね。サークル・モッシュみたいなものも、いわゆる青春の一ページみたいな文化でありスタイルじゃないですか。本当の意味で盛り上がってるか、盛り上がってないかとは関係ないんですよね。
——15年の13th『Burning Tree』から、古巣の〈ポニーキャニオン〉を離れて〈SPEEDSTAR〉へと移籍しました。このアルバムは、それまでの濃密なアプローチに比べると、結構肩の力の抜けた作品となっているように思いますが、それには移籍の影響もあるんでしょうか?
西川 『Burning Tree』は、〈ポニーキャニオン〉にいた頃に半分くらいは作ってたんですけど、代々木にあったスタジオをかなり自由に使わせてもらってたんです。その影響が大きいと思いますね。誰にも何も言われずに、好き勝手作ってたんで。移籍もあって時間がかなりあったんで、ゆったり作れたというのもあって。
田中 考える時間もかなりあったしね。
——ちなみに、このアルバムに入っている“KOL(キックアウトラヴァー)”という曲は、キングス・オブ・レオンとかかってるんですよね?
田中 そうですよ(笑)。いや、結果的にキングス・オブ・レオン色なんか全然ないんですけど。その頃にはジャム・セッションも板についてきて、どうやってネタを探すかっていうところから始まって、「最近、何聴いてる?」みたいな、皆でジャムる前にテーマやとっかかりを決めたりするんです。で、たまたま「キングス・オブ・レオンとかどうですか?」っていう案が出て。自分も数枚持ってて、じゃあこんな気分でやってみようかと。キングス・オブ・レオンを追い求めてっていうわけではなく、その時聴いたキングス・オブ・レオンの気分をうろ覚えでやってみたっていう(笑)。
GRAPEVINE – KOL (studio live 2017)
Kings Of Leon – Use Somebody (Official Video)
——そして、移籍して3作目、20周年を迎えての最新作となる15th『ROADSIDE PROPHET』は、これまでの集大成であり、次の20年へと繋がる新しいスタートラインのようなアルバムなんじゃないかとも感じました。それについて、ご本人はどう思われますか?
田中 まぁ、アルバムに関しては20周年を意識して作ったわけではないので。新しい扉っていうことに関しては、常に違うもんとか、まだやったことのないものが少しでもあればとか、そういう楽しみを見つけながら曲を作ってますからね。
——別に20周年の意気込みなどはなく、アルバムごとに常に新しいものを作ろうという意識で臨んでいるんですね。
田中 アルバムごとというか、曲ごとだと思うんですよね。たまたまその時期に録ってた曲の集合がアルバム、という。だから常に意気込んで作ってはいるんですけど、特に「20周年」だから、という意味の意気込みはないです。本来20周年を派手に祝おうっていうのであれば、例えばベスト盤だったり、リテイクだったり、トリビュートだったりっていう方が分かりやすいんだと思うんです。あんまりそういうのには興味ないですね。
RELEASE INFORMATION
ROADSIDE PROPHET
2017.09.06(水)
GRAPEVINE
20th Anniversary Limited Edition(CD+DVD+ピクチャーフレーム仕様)
VIZL-1216(※VICL-64820 + VIBY-1196)
¥4,000(+tax)
[amazonjs asin=”B073J2Z8VH” locale=”JP” title=”ROADSIDE PROPHET(20th Anniversary Limited Edition)”]
通常盤(CDのみ)
VICL-64820
¥3,000(+tax)
VICL-64820 [amazonjs asin=”B073J3B1TR” locale=”JP” title=”ROADSIDE PROPHET(通常盤)”]
M1 Arma
M2 ソープオペラ
M3 Shame
M4 これは水です
M5 Chain
M6 レアリスム婦人
M7 楽園で遅い朝食
M8 The milk(of human kindness)
M9 世界が変わるにつれて
M10 こめかみ
詳細はこちら
text & interview by 青山晃大
photo by 横山マサト




